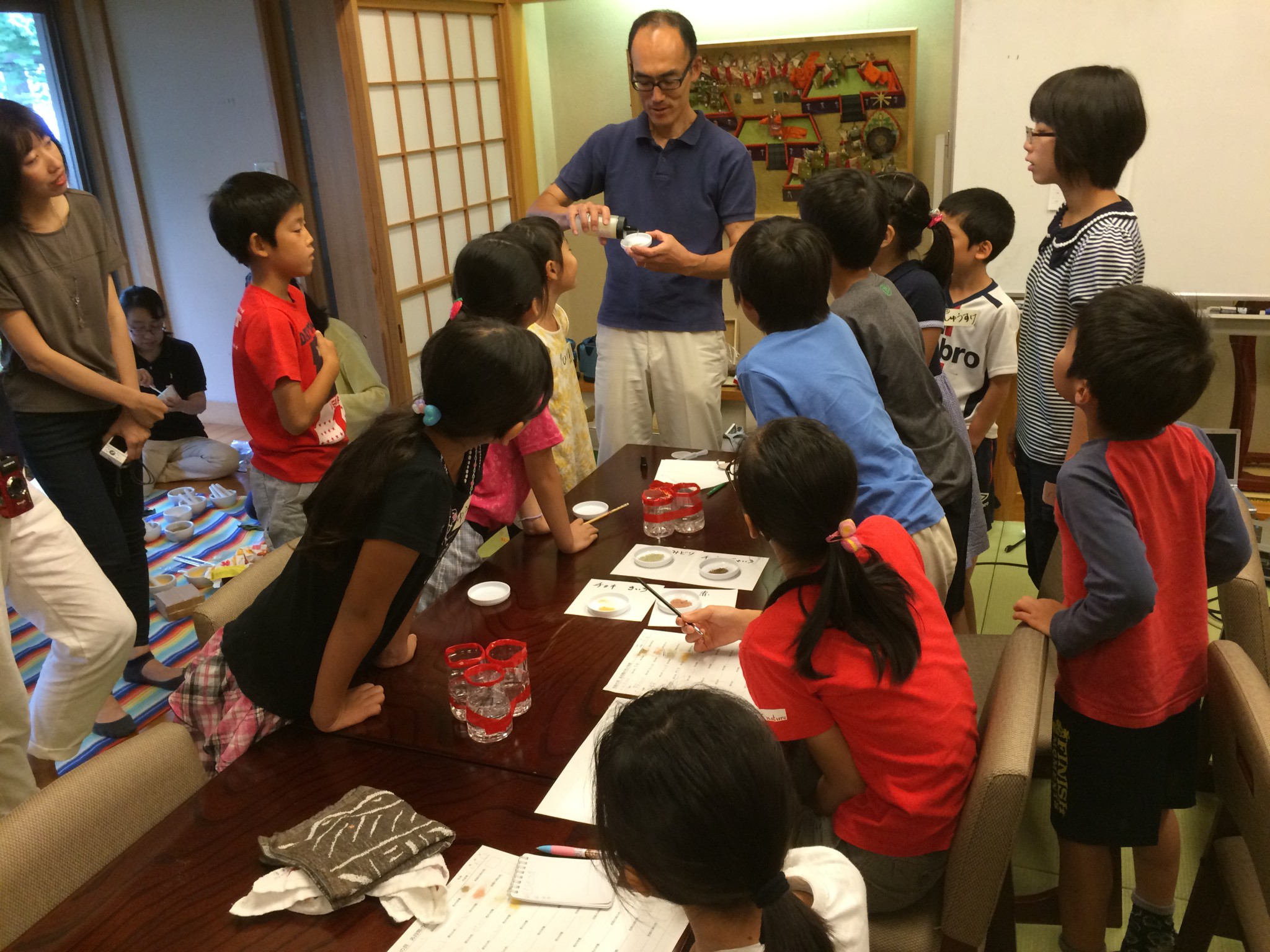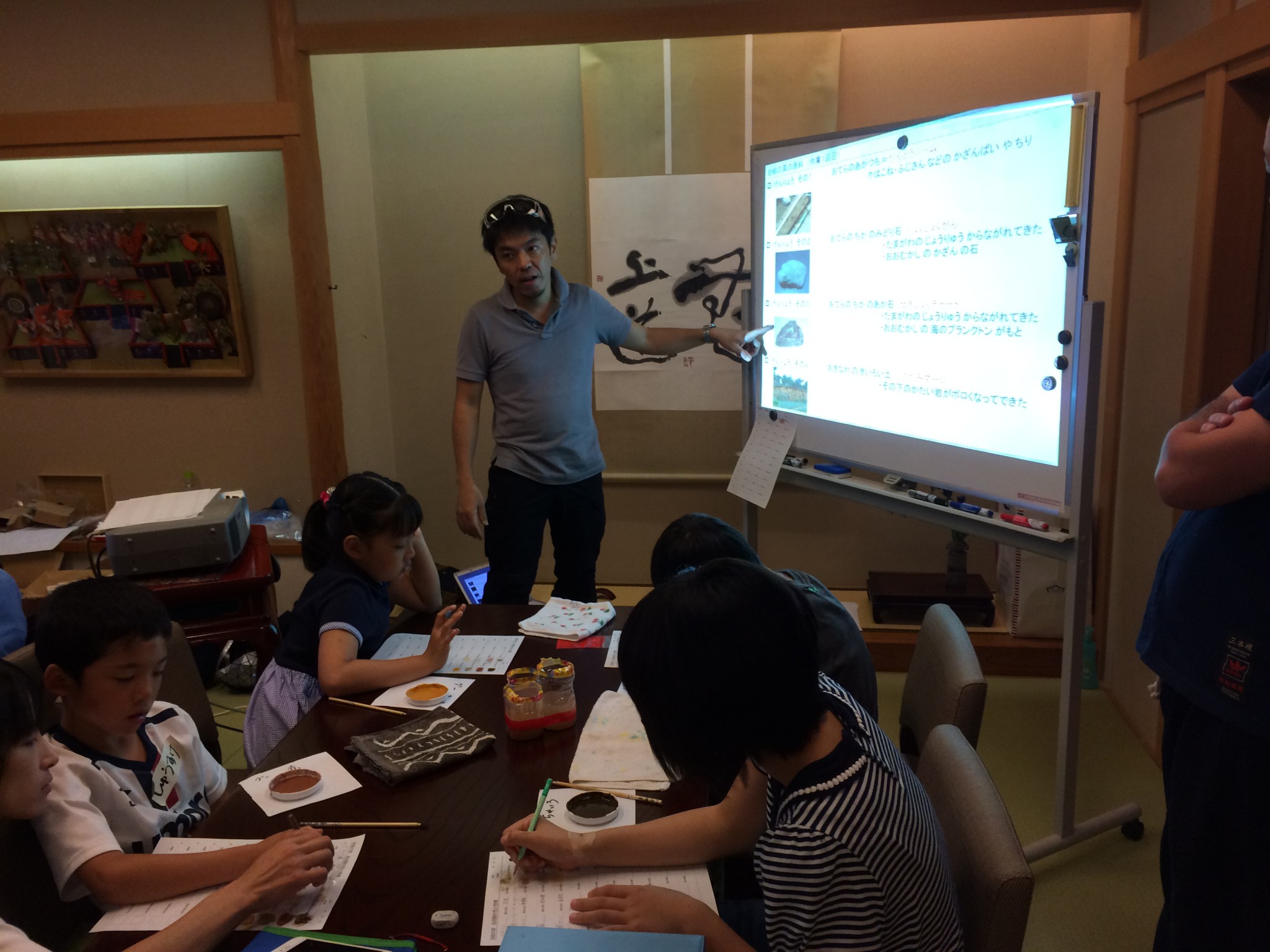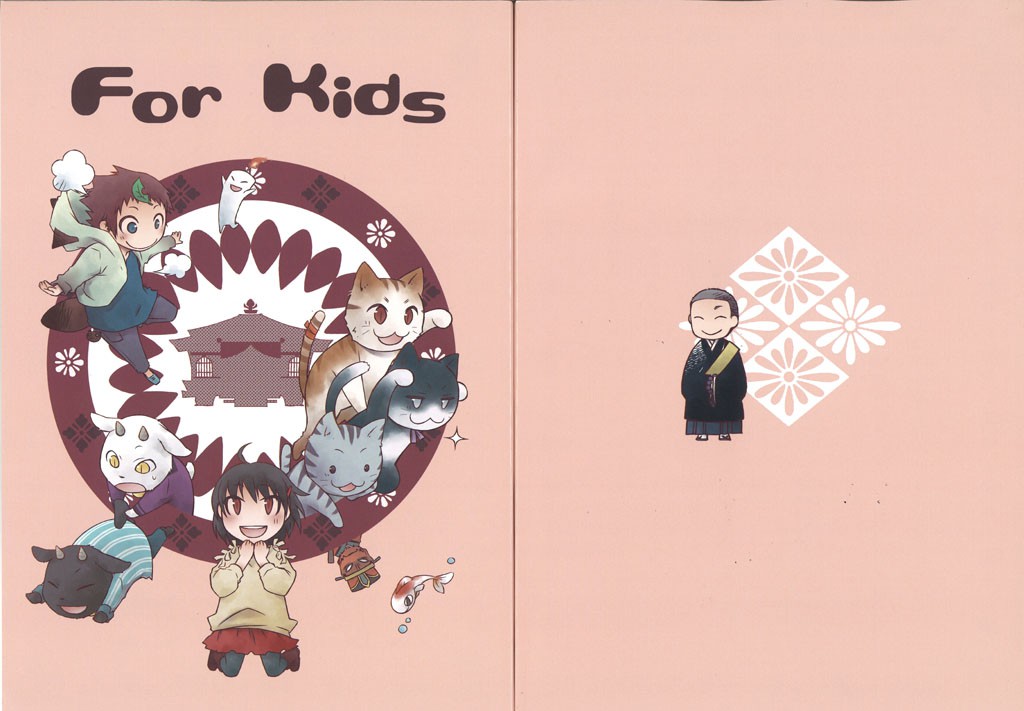In Biwako
2016年11月1日
琵琶湖団体参拝旅行
この度の団体参拝旅行では、滋賀エリアを訪ねました。まずは豊臣秀次を弔った瑞龍寺を参拝。ロープウェイで琵琶湖を見下ろしながら気分良く山をあがったところ、お寺はその先の急な石段の上にあると聞き、一同気合いを入れて登りました。ここは日蓮宗唯一の門跡寺院だそうで、特別な作りの参拝の間等が拝見できました。
続いて見塔寺へ。彦根港から一日一便しか出ていない船で渡る無人島、多景島にあるお寺です。ここもまた、船着き場から急な石段を登った先に釈迦堂があり、頑張ってお参りしました。船の滞在時間が30分しかないので、お開帳後は大急ぎで、島の端にある「南無妙法蓮華経」を彫りつけた大きな岩を見に行き、島を後にしました。
最高齢が94才、足の悪い方も多い我々の団体ですが、夜も元気に食事の後のカラオケを楽しみ、温泉に入って一日目終了。
天気予報で「暴風雨」と表示されていた二日目ですが、きれいな朝焼けを見ながらの朝風呂からスタートできました。比叡山にある横川の定光院へ。ここは、若き日の日蓮聖人が勉学に励まれた所で、21才から12年間、「論湿寒貧(法論の日々、多湿な気候、厳しい寒さ、ひもじい思い)」の中で日蓮聖人が御修行なさったところです。大きな日蓮聖人像も建っていました。
その後、延暦寺世界遺産の根本中堂を参拝したときには「おとめちゃんたちはどこからおいでなさった?」とお坊さんが話しかけてきて下さり、説明を聞くことができました。精進料理の昼食も美味しく頂いて比叡山を下りました。広大な敷地の一部しかお参りできなかったので、またの機会にゆっくり行ってみたい所です。
最後に米原駅近くの龍王寺(団参に数回ご参加の福山上人の御自坊…福山上人は今回の旅ルートも組み立てて下さいました)をお参りして、帰路につきました。心配していた雨にもほとんど降られず、雨用ブーツを履いて参加した私は拍子抜けでしたが、これも、皆さんの心掛けの賜物だと思います。とにかく事故もなく無事に東京駅に着いたときにはホっとしました。(陽子記)